医師は「答え」を持っていない。患者さんの声をどこまでも「聴く」-オープンダイアローグの実践と精神科訪問看護
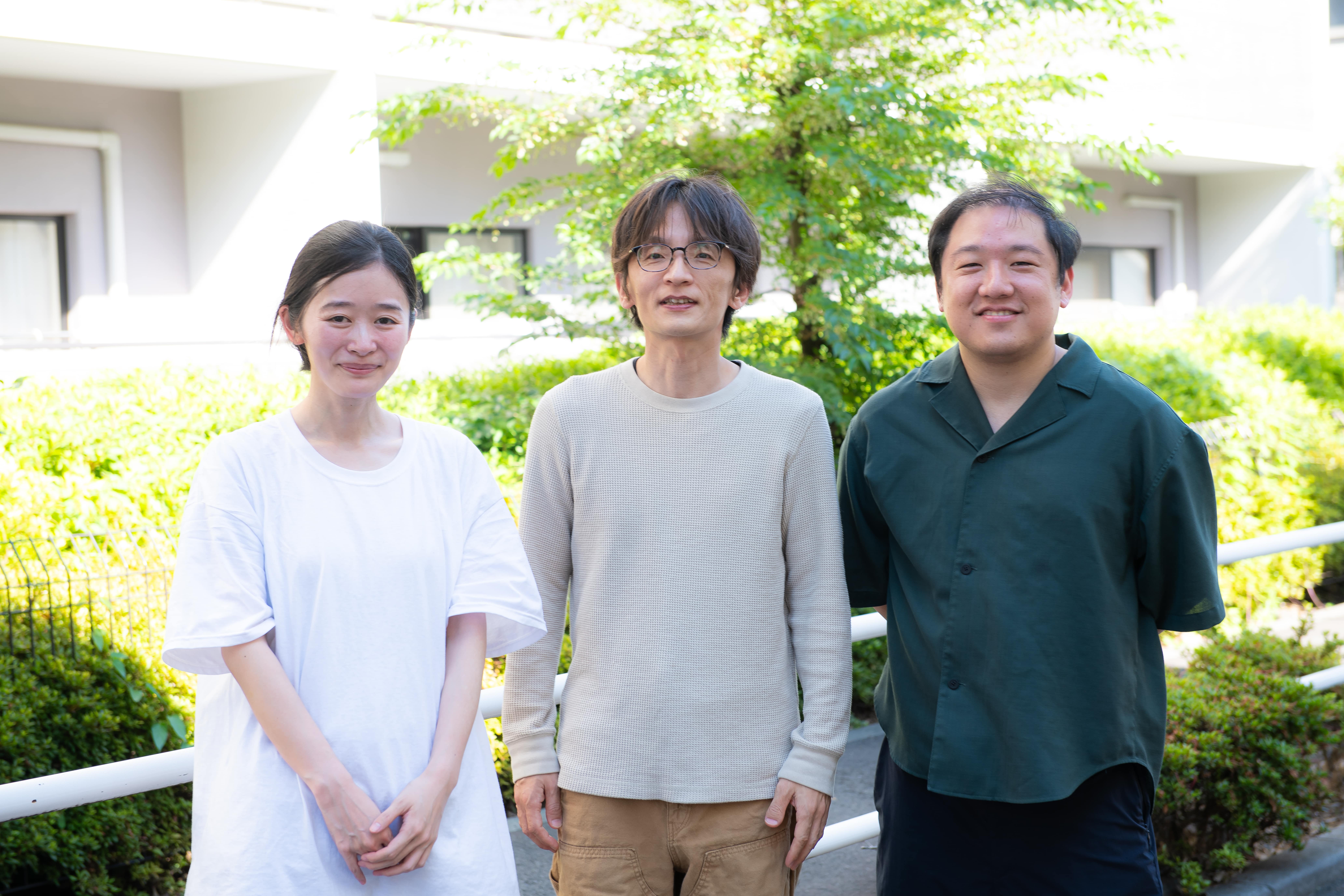
「支援者として、患者さんの話をもっと聞きたい」「患者さんを身体的に拘束するのはつらい体験だった」
そういう声を、現場の対人支援職の方々から聞くことは少なくありません。医療現場の対応によっては、患者さんだけでなく、支援職もまた傷ついているのかもしれません。
精神科医・森川すいめいさんもかつてそうした葛藤を抱えていたといいます。森川さんは現在、患者さん本人やご家族などの関係者とともに対話をつづけていこうと、北欧で発祥した「オープンダイアローグ」を日本で実践しています。オープンダイアローグとの出会いは、森川さんにどのような影響を与えたのでしょうか。
対話を大切にするメンタルケアサービス「コモレビ」代表の森本真輔とサービス管理責任者・看護師の谷澤早紀が森川さんにお話を伺いました。
医師として学ぶ過程で”鎧”を身につけてきた
森本真輔(以下、森本):オープンダイアローグには、「専門家としての鎧を脱ぐ」というコンセプトがあると考えています。森川さんはいい意味で鎧を身につけていないイメージがあります。そんな森川さんにも専門家としての鎧を身につけていた時期はありましたか。

森川すいめいさん(以下、森川):医師という専門家の役割として、勉強すること自体は、これからもずっと続けなければならない大事なものではあります。
しかし患者さんと会話するときに、学んだことを鎧や武器にすることはまた別の話です。私も精神科医になるための研修医時代に、精神医学や認知行動療法などを一生懸命勉強することで、それが鎧のようになっていた時期があり、その頃に出会った人たちには謝罪をしたい思いがあります。
どういうことかというと、本来患者さんの話を聴くことをまず大事にしなければならないのに、たとえばその症状が「うつ病」に当てはまる場合、自動的に「抗うつ薬」を処方する、「あなたはこの診断名に当てはまるからこの治療がいいですよ」というやり方をしていました。
私が短時間の会話で得られる患者さんの情報はすごく限られているなかで、自分の持っている少ない経験を照らし合わせて「答え」を出そうとする仕事をしていたなと振り返って思います。

森本:身に付けた知識、持っている知識に患者さん側を当てはめていくということが、結果として「鎧」となってしまっていたということですね。
コモレビでも、例えば服薬のケースでは、どうして薬を飲む必要性があると思うか、薬を飲むことでどういう効果があるか、まず最初にご本人に尋ねるように気を付けています。「この薬はこういう良いことがあるから、飲みなさい」という姿勢では、それこそ「鎧」を着たままの関わりとなってしまうと思っています。
オープンダイアローグの原則を踏まえて、コモレビがなすべきなのは、ご本人の主体性を尊重し、ありたい姿を実現するためのサポートだと考えています。
医師として働くなかで抱えていた問題意識
森本:当時抱えていたもどかしさに対してどのように対処されたのでしょうか。
森川:当時、ホームレス状態にある人たちのいる支援現場にいたのですが、支援側に意思決定権がないという経験をできたのは、幸いなことでした。おかげで、医療側が力を持って患者さんのことを勝手に決めていく在り方にちゃんと違和感を持つことができたんです。
具体的には、診療時間がものすごく短かったり、隔離室の運用だったりなど、組織や病院がつくったルールに患者さんたちを当てはめていくことに、疑問をたくさん抱いていました。

隔離室に強制的に連れてこられた患者さんのなかには、当然抵抗する人もいます。そのときに、拘束することをせず、「ごめん、怒ってるよね」「何があったの」「怖いよね」と言葉を探しながら会話をしていると、ひどく傷ついていることが分かるんです。そうすると、少しずつ患者さんの怒りや不安も収まって、会話になっていきます。結局私が拘束指示を出したのは一人だけでした。その方は60分だけ、アルコールの離脱症状で点滴をしなければならなかったときでほとんどの時間を一緒にいました。
森本:身体拘束をせずに済むケースを目の当たりにされて、身体拘束をするかどうか決める流れに問題があるのではないか、と疑問に思われたんですね。
コモレビは病院ではなく地域にフィールドがあるわけですが、フィールドが変わると医療者と利用者さんの力関係が変わります。地域では利用者さんは自由に生活していますので、強制することは難しい。そもそも強制すべきでもないと思っていますので、僕たちは利用者さんが自由であり続けるためのサポートを担っていると思っています。
オープンダイアローグとの出会い
谷澤早紀(以下、谷澤):そんな日々のなかで、どのようにオープンダイアローグと出会ったんですか。
森川:友人が「オープンダイアローグ、知ってる?」と声をかけてくれたんです。名前を聞いて、「『オープン』という言葉が好きだな」と思ったのが第一印象でした。
2015年、フィンランドへ行って、オープンダイアローグの生まれたケロプダス病院を見学しました。この病院では1984年のある日、対話主義を宣言してオープンダイアローグを一日で誕生させました。私もそれに習おうと、帰国した翌日からオープンダイアローグの実践を開始しました。
「オープン」とは、クライアントである本人やご家族などの関係者に対して開かれているという意味です。その人のいないところで勝手に物事が決まらないようになっています。
それまでの、こちら側が力を持って患者さんのことを勝手に決めていく医療のように、こちらが知りたい病状を訊くのではなく、「何に困っているのか」「ここに来たかった理由は何か」「どういう経緯で来たのか」「どんな期待を持って話そうとしているのか」「どんな話がしたいか」というところからはじめるとぜんぜん違います。本人の声をちゃんと聴くということが大事です。

森本:コモレビでも、困りごとに翻弄されている方がいらっしゃるときに、その困りごとにラベルをつけて薬を処方するという方法ではなく、ご本人が困っていることにじっくりと耳を傾けることで、コモレビとご本人の関係性が変わっていったことがあります。
精神科訪問看護という枠組みを活かした対話の実践への期待
森本:僕は、2016年に斎藤環さんのトレーニングセッションに参加して、改めてオープンダイアローグが面白いと思いました。精神疾患とは、ご本人の認識している世界と、自分が「こうありたい」と考えている対人関係や対世界のあり方とに齟齬があるときに発症するものではないかと僕は考えています。オープンダイアローグはその齟齬を解消してくれるコロンブスの卵に感じられたんです。
森川:精神疾患をもつ人は、周囲の人からの否定や人間関係のこじれに悩んでいることも少なくありません。オープンダイアローグは、いったんそうした否定やこじれのない対等な他者に囲まれることで、回復した後の世界を疑似的に体験することができます。それを続けるうちに、ほんとうに回復していくという面白さがあります。

森本:オープンダイアローグを取り入れるなら、訪問看護がいいかもしれないと思いました。対話する時間をちゃんと取りつつ採算が合う制度は日本には訪問看護しかないように思います。また医療保険の枠組み内で行うことで、たとえば生活保護を受けている人など、どんな人にもオープンダイアローグを届けることができます。
森川:そうですね。日本の制度の中で、訪問看護という枠組みを使えば、経済的に余裕のない人たちにもオープンダイアローグを届けることができると私も考えていました。そう思うのと実際に行動することは違うので、コモレビにはとても興味を持っていました。実際に会ったら、いい人たちでしたし、希望を抱きました。
コモレビさんでも対話の時間は40分にされていますが、経営とのバランスを考えると、それくらいが限度かなと思います。
森本:できるなら60分やりたいんですけどね……。
対話の大切さについて
森本:「オープンダイアローグをやれば、すぐ治るんですか」と分かりやすい治療を渇望する患者さんもいらっしゃいます。
森川:その奥にあるのは、「心から助けてほしい」という思いです。その声を大事にして「一緒に考えてみましょう」というはじまり方をします。すぐに答えは出ません。だから答えが出るまで一緒に考えるのがオープンダイアローグです。
オープンダイアローグのゴールは、医療チームと本人の関係性が良くなることではありません。たとえば本人と家族の課題があるとしたら、本人が生きやすくなるために、家族と関係性の困難が解消されることを目指します。本人が生きやすくなることをめざして、コモレビさんは「だれかと話せたら楽になる」ということをとても大事にしているように感じています。
谷澤:本人の人生がいい方向に進んでいくことが大事ですよね。
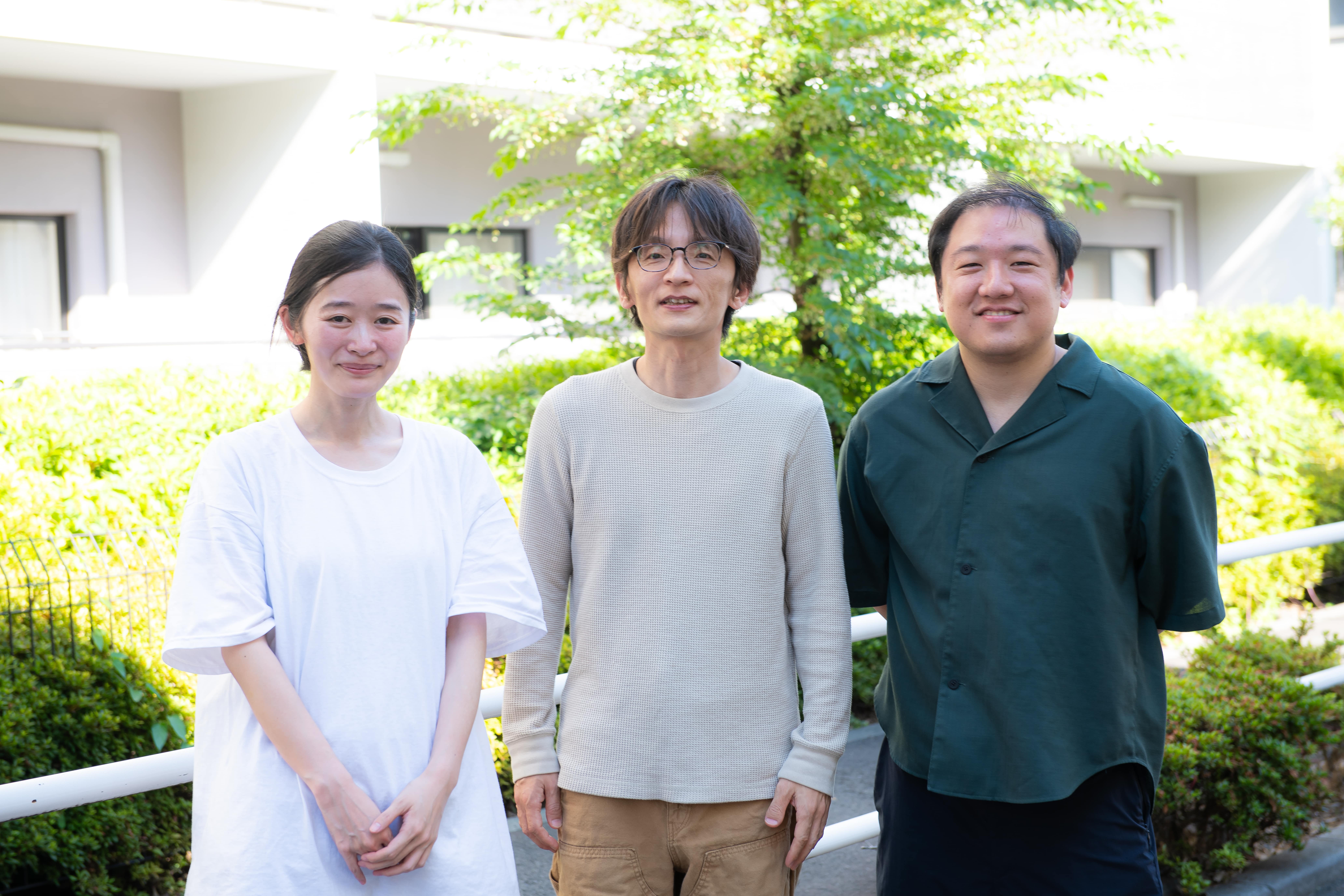
コモレビでは、森川さんのようにオープンダイアローグを実践する医師とも連携して、精神科訪問看護のサービスを提供しています。現在、共に働く仲間を募集しています。私たちと一緒に、利用者さんが「ありたい姿」に向けて一歩ずつ進んでいくのをサポートしてみませんか。採用情報の詳細はこちらをご覧ください。
「コモレビ」サービスサイトでも、森川さんとオープンダイアローグの出会いや、クリニックでの実践についてのインタビュー記事を掲載しています。こちらもぜひご覧ください。
こころの悩みを抱える人が、ゆっくりと対話できる場をー精神科医・森川すいめいさんが取り組むオープンダイアローグと、精神科訪問看護への期待
