対話が看護を変える ― 精神科病棟から訪問看護にたどり着いたふたりの看護師の歩み
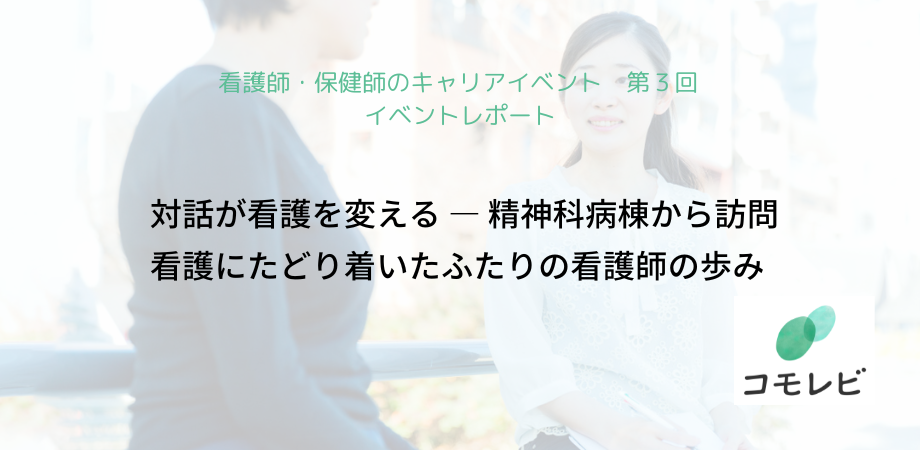
「精神科で働いているけれど、病棟では一人ひとりの患者さんに使える時間が限られていて、できればもっとしっかり一人ひとりとかかわりたい」
「精神科に入院する患者さんのケアにかかわる中で、重症化に至る前の早期介入が重要だと感じている」
現在、精神科病棟で働いている看護師さんの中には、こうした思いや葛藤を抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
私たちコモレビナーシングステーションは、「精神科病棟から退院してきたばかりの方」から、「会社に通い、ぎりぎり社会との接点は保てているものの、精神疾患に悩まされ続けている方」、「精神疾患が重症化する前に、予防的な介入をすることが望ましい方」まで、従来の精神科訪問看護が主な利用者としては想定してこなかった方々をはじめ、さまざまなニーズを持った利用者さんに「対話を通じたメンタルケア」を提供している精神科訪問看護です。
コモレビでは、多種多様な経歴を持つスタッフが働いており、中には精神科病棟勤務の経験を活かして転職し、現場で活躍しているスタッフもいます。
今回、「精神科病棟での経験を活かしたメンタルケアの仕事」と題し、精神科病棟勤務を経てコモレビに入社したスタッフ2人に、病棟時代のお話やコモレビとの違いについてのお話を聞きました。この記事では、その様子の一部をお届けします。(聞き手:コモレビの前田、伊藤)
看護師になったきっかけ

--看護師という職業を選んだきっかけを教えてください。
永井光咲さん(以下、永井):職業に看護師を選んだのはたまたまだったのですが、高校生のときにひきこもっていた経験や、看護実習のときに精神的な疾患を抱える方とかかわったことから、精神科看護の面白さを感じ、新卒から精神科病院に就職しました。
長野優美さん(以下、長野):家族の死をきっかけに、人に寄り添える看護師になりたいと思って、看護師を志しました。学生時代、実習中にがんの患者さんを受け持ち、もっとがんについて学びたいと思って、がんの専門病院に入職しました。
病棟での経験と気づき

永井:最初の3年間は慢性期病棟で働きました。そこでは30~40年と長期入院されている方が多く、その方たちにとっては病院が生活空間そのものでした。その中で、患者さんと対話しながら年単位で体調を見ていく経験をさせてもらい、しっかり対話することの面白さや大事さを感じました。
その後1年間、急性期病棟で働きました。退院して地域に戻っても居場所がなかったり相談できる場所がなかったりして、入退院を繰り返し、悪化してしまう方が少なくなく、普段の生活の中での体調管理や入院する前のケアが大事だと感じました。
長野:がんの専門病院で働く中で、スタッフが精神疾患を併発している方の看護を敬遠していることに疑問を持つようになりました。また、時間がある時には患者さんと話すことを心がける中で、患者さんとコミュニケーションすることの大切さを感じ、もっと精神疾患について学びたいと考え、精神科へ転職しました。
精神科病棟で勤務する中で、対話を中心とした看護の経験をさせてもらいました。比較的軽い症状の患者さんが入院してきた時に、周りの患者さんと比較して「自分は軽症だから」と退院し、しばらくして再入院される方が少なくなく、支援を求めてきたにもかかわらず、適切な治療が提供できないことに疑問を感じ、退院前後の支援ができる精神科訪問看護に興味を抱くようになりました。
精神科訪問看護「コモレビ」への転職理由

永井:生活の中での体調管理や入院する前のケアの大事さを考えて訪問看護を検討し始めました。その中でコモレビは対話を重視しているところと、幅広い利用者さんがいる点にとても意義を感じて入社しました。
精神科訪問看護は一般的に、患者さんの退院時に、病院からケースワーカーさんやソーシャルワーカーさんを経由して入る形が多いのですが、コモレビではそういう形もある一方で、入院はしたことがないけれど困り感や精神的不調を抱えている方もいらっしゃるんです。
--グループホームや保健師など、訪問看護以外の選択肢はありましたか。
永井:いいえ、訪問看護一択でした。対話をしっかりする時間を取れるのは、訪問ならではだと考えていました。
長野:私は精神科訪問看護の中でも、利用者さんの尊厳を大事にしていたり、スタッフも利用者さんと真剣に向き合っている、そして初期の精神的な不調のある人への支援ができるコモレビを選びました。
コモレビで働く中で、自分自身の人生について深く考える機会があって、自分がやりたいことはなんだったかを考えたときに、留学に行きたかったことを思い出しました。コモレビ代表の森本さんに相談した結果快く送り出してもらい、コモレビを退職して、今は海外にいます。
病棟とコモレビの違い

--お二人ともありがとうございます。病棟とコモレビの違いとしてどういうことを感じるか、教えていただけますか。
長野:病棟だと、症状が悪化した時も状態が安定してきた時も、どうしても病院内の「ルール」があるので、それを守ってもらわなければいけないという点で、看護師が患者さんより上の立場で発言することが多かったです。このように、病棟ではどうしても強制力が働いてしまうので、患者さん主体で治療を進めることがむずかしい面があります。
それに対して、コモレビは利用者さん主体の看護を実践しているので、強制力が働くことはありません。コモレビに来てからは、看護師も利用者さんも同じ目線に立って、利用者さんの話したことを中心に対話を進めていくというのが印象的でした。
永井:長野さんのおっしゃるように、私も病棟の時に看護師と患者さんのパワーバランスを感じていました。病棟だと、患者さんの症状の危機的な状況に対してどう対処するかという、患者さんと治療者双方が合意するためのクライシスプランを作成します。
退院前にそれを一緒に作って、「こういう不調のときはこういう対処をしましょうね」と決めるけれど、そのときに治療側が願って作っている部分が大きく、実際に患者さんがそのクライシスプランを自分で使っていたかというと疑問が残ります。
それを例にとっても、病棟では治療する側つまり看護師がルールを管理したり指導することが多く、利用者さんが主体的に自分の責任を感じられる機会をつくるのがむずかしいと感じていました。
その意味でも、コモレビでは患者さんがやりたくないことや興味のないものを積極的には勧めないし、必要なものは、一緒に試しにやってみることを提案する等、フラットな関係で、やってみるかどうか利用者さんが主体的に選択するための時間をかけられる側面があります。
精神科病棟での経験が精神科訪問看護で活きた例

--コモレビで病棟での経験を活かせたと感じたことはありますか。
永井:病棟だと、私の場合は、統合失調症や双極症の方を多く見ていました。いずれの方も不調時は表情が明らかに普段と違ったり、特徴的な言動をされたりするので、不調を早く拾うという意味では病棟にいた経験が生きていると感じます。
長野:病棟での学びが精神科訪問看護で活きた例として、病棟で患者さんの症状悪化を経験してきているので、そのサインに気づき、早めにチームで相談して、重症化を防ぐために何をすべきなのかを明確にして訪問に臨むことができていました。
薬の副作用も病棟で学んでいたので、副作用を早めに軽減できるようにアドバイスしたりしたこともありました。また、自傷他害のリスクの高い利用者さんに対して冷静に対応できたこともあります。
訪問看護での難しさと向き合い方

--病棟との違いについて、訪問看護とのギャップを感じて難しいことはありますか。
永井:病棟の時は統合失調症の患者さんを多く見ていました。今は発達障害や双極症や鬱の方が多いです。まずその違いがあり、発達障害などは一から勉強し直しました。とはいえ病名が困りごとではありません。症状から来る働けないことやお金が稼げないこと、対人関係がうまくいかないことなど、利用者さんの困りごとは病気ではなく生活にあります。
生活をどう整えていくかということに取り組まれる利用者さんもいれば、根本的な考え方の癖をどうにかしたいという方もいらっしゃったりと、利用者さんのニーズはさまざまです。限られた訪問の時間で、その人のありたい姿に向かって対話でどう伴走していくのか、勉強したり実践したりするのは、とても難しいと感じています。
長野:利用者さんのありたい姿に向かって目標を明確にしていったり、そのために訪問看護で何をすべきかを考えたり、40分をどう有効活用していくかを考えたりすることは、私もけっこう難しかったです。特に、ご本人に対話に意味を見出していただくのが難しいと感じたときは悩みました。その時は、チームに早めに相談して、自分の違和感を解消しながら他のスタッフに同行してもらって、対話を修正していくことで改善していきました。
永井:それから、病棟は看護師同士のお互いが見えやすいチーム看護である一方で、訪問看護は1対1で利用者さんとかかわる中で、どうチームで利用者さんに対して支援するかが問われる点が病棟との違いだと思います。
--チームで支援するために工夫していることはありますか。
長野:困りごとがあったり違和感のある訪問だったときはすぐにチームに連絡し、次の訪問で何をするかを明確にしていました。カンファレンスで、次の時間をどう有効に使っていくかを話し合っていました。スタッフ同士のコミュニケーションはよく取れていたと思います。
利用者さんとの対話を通して、自分自身が変わっていった

--先ほど長野さんから、コモレビで働く中で自分自身の人生について深く考える機会があったというお話がありましたが、利用者さんとの対話を通してご自身を見つめ直した経験はありますか。
長野:利用者さんとの対話が、自分の人生を振り返る機会になっていました。利用者さんの目標を明確にしていく支援はできましたが、実際に利用者さんが目標を言語化する姿を見ていて、これは苦しいことでもあるだろうなと感じていました。
だから、利用者さんだけではなく自分も目標を言語化してみようと思いました。自分の使う言葉の定義なども見つめ直していくなかで、訪問を重ねるたびに自分がやりたかったことを実感するようになっていきました。海外の患者さんにもかかわらせてもらうことがあり、海外の人が感じる孤独感を自分でも体験してみたいと考えてカナダへ留学に来ました。
永井:利用者さんに「自分のありたい姿」や「1、2年後どう過ごしたいか」と聞くけれど、自分に置き換えると確かにむずかしいです。私の場合、利用者さんによって緊張したり気が楽に感じたりすることがあります。そのことから、自分には相手に合わせる、期待に応えようとする傾向がある、期待に応えられないと緊張が高まることがあることがわかりました。結果的に利用者さんのこともわかるし自分のこともわかって、双方向に理解が深まると感じています。
おわりに

永井さんも長野さんも精神科病棟の経験を活かしてコモレビに入社してくれ、利用者さんに対話を通したメンタルケアを提供してきました。お二人とも利用者さんとの対話を通して、自分自身が変わっていきました。コモレビの提供する対話を通したケアは、利用者さんだけでなく支援者をも変えるという意味で、フラットな地平に立ったものであると言えるのではないでしょうか。
この記事を最後まで読んでくださった看護師の方で、ご自身の次のキャリアとして、精神科訪問看護やコモレビにご興味を持ってくださった方には、コモレビをより知っていただける機会を用意しています。詳細はこちらからご確認いただけます。
