2025年7月18日(金)対話を通して一人ひとりとかかわる~養護教諭から精神科訪問看護コモレビに転職したふたり~
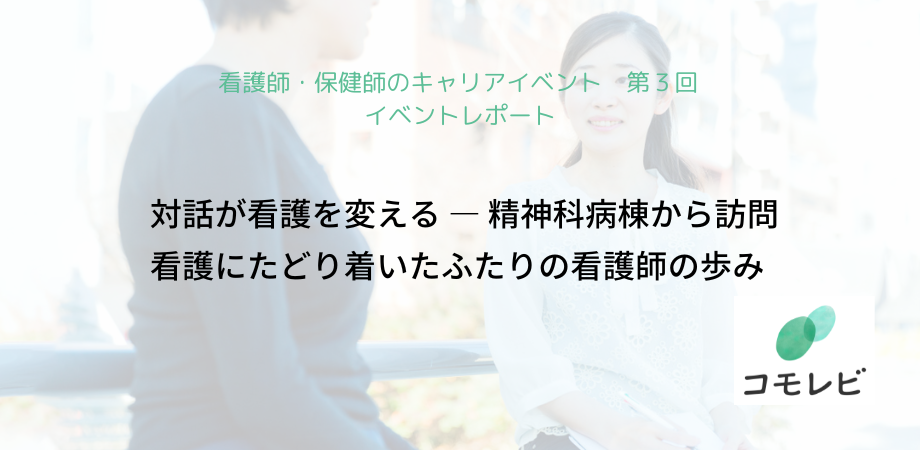
「精神科以外で看護師として働いているが、『こころ』に関わる仕事に関心がある」
「看護師として働いているが、事務的な仕事よりも、患者さん・利用者さんとかかわり対話することにもっと時間を割きたい」
「精神科、精神科訪問看護へのキャリアチェンジを検討しているが、不安を感じている」
現在、精神科訪問看護に関心をお持ちの看護師さんの中には、こうした思いを抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
私たちコモレビナーシングステーションは、「精神科病棟から退院してきたばかりの方」から、「会社に通い、ぎりぎり社会との接点は保てているものの、精神疾患に悩まされ続けている方」、「精神疾患が重症化する前に、予防的な介入をすることが望ましい方」といった、従来の精神科訪問看護が主な利用者としては想定してこなかった方々をはじめ、さまざまなニーズを持った利用者さんに「対話を通じたメンタルケア」を提供している精神科訪問看護です。
コモレビでは、多種多様な経歴を持つスタッフが働いています。
2025年7月18日(金)に開催した「『精神科未経験』で、さまざまな職種からコモレビに入社した人たちのリアルな声~大学病院、養護教諭…多様な経験を経ての、精神科訪問看護との出会い~」では、2人のコモレビスタッフにこれまでのキャリアと現在の仕事について聴きました。
この記事では、当日の内容の一部をご紹介します。
(聞き手:コモレビの伊藤)
病院、養護教諭としてのキャリアを経てコモレビへ
ーーお二人のこれまでのキャリアと、コモレビに入ろうと思った理由について聞かせてください。
吉田:私はもともと養護教諭になりたいと考えていたんです。小児科や中高一貫校の看護師としての勤務を経て、夢が叶って小学校の養護教諭になることができたのですが、実際に働きはじめてみると、どこかで「満たされなさ」を感じていました。
養護教諭の仕事では、健康診断などの事務作業がとても忙しく、子どもたちと直に話す機会がなかなかありませんでした。このとき「自分はしっかり対話をして、1人ひとりと関わりたいんだ」と気がついたんです。
児童精神科に通っている子どもたちの中で、看護師さんと話す中でいやされたり、自己理解が深まったりする子がいるのを見ていたので、最初は児童精神科のクリニックに転職しようと考えていました。転職活動の過程で偶然コモレビを知り、「世の中にある不条理や不公正を生み出す『構造』の解消・是正」を目指しているという点に共感しました。
養護教諭時代に「養護教諭一人ががんばってもどうにもならないことがある」と感じていました。
たとえば保健室登校ひとつとっても、どこまで受け入れるかは学校ごとに違っていて、あまり受け入れないという学校もある。学校、社会全体といった単位で変わっていかないと、解決されないことがあると感じていました。
そうした中で、コモレビの「社会構造にアプローチする」というスタンスにとても魅力を感じたんです。
西田:私も学生時代から「いつか養護教諭になりたい」と思っていました。
まずは看護師としての経験を積もうと、大学卒業後は大学病院で看護師として勤務しました。夜勤の辛さから退職を考えたタイミングで養護教諭の求人を探してみたら、小学校の養護教諭の臨時採用の募集を見つけ、採用が決まりました。
養護教諭として実際に働く中では、環境調整の重要さを実感しました。
当時がコロナ禍であったということも大きかったと思うのですが、子どもたちに多様な力があっても、環境によってその力が発揮できなくなってしまうことがあるのを目の当たりにしました。特に、集団になじみにくい子、発達に困りを抱えている子にとって、環境の影響は非常に大きいと痛感しました。
発達のこと、環境調整に関することなど、様々な知識が必要な状況でしたが、自分にはそれらが不足していました。しかし養護教諭は一人職なので、特に医療や福祉、療育に関する知見を得ることは難しかったんです。
そうした方面をもっと学びたいと仕事を探している中でコモレビを知りました。
環境調整はまさに「社会構造」につながる部分なので、社会構造にアプローチするというコモレビのミッションにとても共感しました。
私にとっての軸はずっと「子ども」でしたが、大人も子どもも基本は一緒ではないか、大人、子どもの両方のケアを幅広く経験できることも自分の学びにつながるのではないかと考え、コモレビに入社しました。
「一人ひとりと向き合うこと」を大切にしたいと考えたきっかけ
ーー二人とも、これまでの経験を経て、「一人ひとりと向き合うこと」を大切にしたいと考えている印象を持ちました。そこに至るまでには、どのようなきっかけがあったのでしょうか。
吉田:
これまで接してきた子どもたちの困りごとは、一人ひとりさまざまでした。発達障害などの生まれ持った特性でなかなか環境になじめないという子もいれば、教育虐待を受けている、ヤングケアラーとなっていて自分に目を向けてもらえないなど、本当にいろいろな困りごとを聞きました。
それぞれの状況に合わせた支援が必要だけれど、担任の先生が個別にフォローするには限界があるし、スクールカウンセラーさんの予約もなかなか取れなかったりしました。
もっと力になりたいと思いながらも、私自身は他の仕事が忙しくて手が回らないという状況の中で「もっと一人ひとりと対話をしたい」と強く感じるようになったのだと思います。
西田:病棟で働いていた時、養護教諭をしていた時、両方で「もっと対話の時間をもちたい」と思っていましたね。
呼吸器・甲状腺の病気を専門とする病棟でしたが、とても忙しくて患者さんとお話する時間はなかなか持てませんでした。しかし、痛みや入院生活の辛さについてお話を少しでも聞けたら、患者さんの心が和らぐのではないか、と思っていました。
養護教諭のときも、事務作業が多く、保健室に来てくれている不登校の子どもたちが隣にいるのに、なかなかお話できなかったです。人とかかわろうという気持ちを持って学校まで来てくれたのに、一人で本を読んでいたり、課題をやっていたり、突っ伏していたりしている彼らに「大人の事情でごめんね」と心の中で謝ることも多く・・とてももどかしかったです。そうした中で、より1人ひとりと対話をすることに自分のエネルギーを向けたい、と思うようになったのだと思います。
コモレビで働いてみて
ーー実際にコモレビで働く中で大切にしていることや、働いてみて感じていることがあったら、教えてください
西田:「その人がどういうふうになりたいのか」「どのように生活していきたいのか」などは支援をしていく上での軸になるので、できる限り丁寧に聞いていきたいと思っていますね。
「ありたい姿」「どんな生活がしたい」などは、誰しもが1秒ごとに変わっていくようなことですよね。過去のその人の言葉も大事にしつつ「今この状況ではどうなのかな」を、推測するだけではなく、言葉で聞くことの大切さを、最近改めて実感しています。
「これを聞いたらまずいかも」「聞くのはちょっと怖いな」と思うときもあるのですが、聞くべきことは聞いておかないと、私の想像で話が進んだり、目の前にいるその人ではなく「私が想像しているその人」になっていってしまうこともあると思っています。
吉田:「苦しさ」がないというのが一番大きいと感じています。
病院にいたときは、患者さんが嫌がることを説得してやってもらう、ということが多くありました。
コモレビでは、一人の人として利用者さんと接し、その人自身の「ありたい姿」「送りたい生活」を叶えるために伴走することを大切にしています。内服したくない人だったら、内服を強制するのではなく「どうして飲みたくないんですか」というところからお話ができます。「強制する苦しさ」がない、「人としての辛さ」がないことは、個人的には一番大きいですね。
また、支援においてはその人の想いがのった「ありたい姿」「生活像」などを共有することを大事にしています。主体性を引き出すうえでこれらのことはとても大切ですが、だからこそ焦って見つけようとはせず、その人自身がどこに向かっていきたいのかを探し続ける姿勢を持つこと、変化があればアップデートして、共有することを大切にしています。
精神科未経験で大変だったことは?
ーーお二人とも精神科未経験でコモレビに入社されましたが、大変さ、難しさを感じたことなどはありますか?
吉田:精神科未経験だったので、疾患の勉強などは必要でした。
また「利用者さんの力になりたい」と思うあまりに、利用者さんの私への依存度を高めてしまい、結果的にその人の力を奪ってしまったと感じたケースもありました。
「あれもやって、これもやって」と求められたときに、よかれと思って応えることが、その人自身の考える機会を奪ってしまうこともあるのだと学びました。
入社してすぐの頃は、こうした状況に陥ったときにどうしたらいいのかわからず、戸惑うことがありました。他にも、「支援がうまくいってない」と感じ、気持ちがしんどくなるときがありました。そうしたときは社内の人に相談したり、話を聴いてもらったりしてきました。
西田:コモレビの利用者さんには、ご家族や地域の保健師さん経由などでつながって、「よくわからないけど、とりあえず」利用を開始されたような方もいらっしゃいます。
「今日は調子が悪いから、訪問は無しで大丈夫です」と言われるときもあって、最初はとても悩みました。私たちとしては、調子が悪いときにこそお話をさせていただいて、どうしたらいいかを一緒に考える上でのヒントを得たいのですよね。どうしたら継続的な対話ができるのだろうと悩みました。
私も吉田さんと同じく、チームのメンバーに相談させてもらうことが多かったです。
訪問に慣れてくると、困ったことがあっても「社内で相談できる人がいる」という安心感を持って訪問に行けるようになっていきました。社内の情報共有ツール(Slack)を使ってコミュニケーションをとったり、社用携帯で電話したりすることも不安の解消につながりました。また、カンファレンスでは顔を合わせて話ができるので、かなり不安感を軽減できると感じています。
チームとしてのコモレビ
ーーお二人とも、チームの仲間と支え合ってきたことが伝わってきました。お二人からみて、コモレビは、どんな職場だと思いますか?
西田:前の職場や新卒のときの病院とは、少し雰囲気が違うなと思いますね。それぞれ良い雰囲気だったのですが、コモレビは特に、穏やかに・建設的に対話をしようという姿勢が職員同士にあると思います。
だからこそ、困ったときに「これを言ったら馬鹿にされるかな」「こんなこともわからないのかと思われないかな」という心配をせず「困っているから、誰かに相談しよう」と、誰にでも声をかけることができているなと。
吉田:これまで、症状の一環で出る利用者さんの攻撃的な発言に自分の気持ちが揺れたこともありました。利用者さんが他のメンバーに対して攻撃的な発言をしているのを聞いてしまったときもありました。
そういったとき、「どういう状態・症状・困りがあって、その発言が出てきているんだろう」と考えることができるのがコモレビの人たちだなと思います。
だから私も、自分が揺れているときであっても率直にチームの皆に話したり、背景やその後の対応などについても一緒に考えることができていると思います。
また、コモレビで働いていて良かったなと思っていることがもう一つあるんです。利用者さんに「ありたい生活は」と聴き続けていると、自分自身にも同じことをずっと問い続けている感覚があるんですね。
コモレビに入社してから3年間、「自分自身は何をしたいんだろう」とずっと考え続けていました。
私は養護教諭という夢を叶えたけれども、「何かが違った」と感じて今に至ったという経緯があり、長期的な方向をずっと模索してきた3年間でした。「自分は何をしたいんだろう」とゆっくり考え続けられる環境があることをすごく幸せに思います。
同時にコモレビには、経営陣をはじめ、理想があり、そこに向けて手段を選ばずに「できることには手を尽くす」というスタンスの人たちが多いので、「人生っていろんな可能性があるんだな」と皆さんから学んでいます。
そうした人たちの姿を見ていて、自分は自分で限界を決めてしまっていたな、自分にももっと色々なことができるかもしれないな、と励まされています。
そうしたことを、個人的にとても幸せに思っています。
森本(コモレビ代表):吉田さんの「自分のありたい姿は何だろう」と自分に問いかけるというのはとても素敵ですよね。利用者さんと対等に関わってるからこそ、問いがそのまま返ってくるんだと思います。「この人は患者で、自分は支援者だから」というスタンスであれば、起きないことだと思います。-
おわりに

いかがでしたでしょうか。養護教諭、病院などさまざまなキャリアを経てコモレビで活躍する2人の話から、何か感じていただけたことがあれば幸いです。
▶コモレビで働くってどんな感じだろう?と思われた方へ
コモレビでは定期的にイベントや採用説明会(転職を考えていない方のご参加も大歓迎です)を開催しておりますので、ぜひお気軽にご参加ください!現在募集中のイベント情報はこちらよりご覧いただけます。
また、コモレビの支援、育成体制、職場環境などについては「カルチャーデック」(こちら)よりご覧いただけます!
